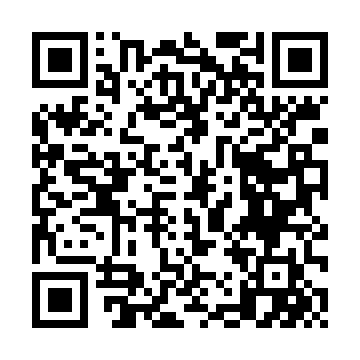対応症状
膝内側側副靭帯損傷ついて
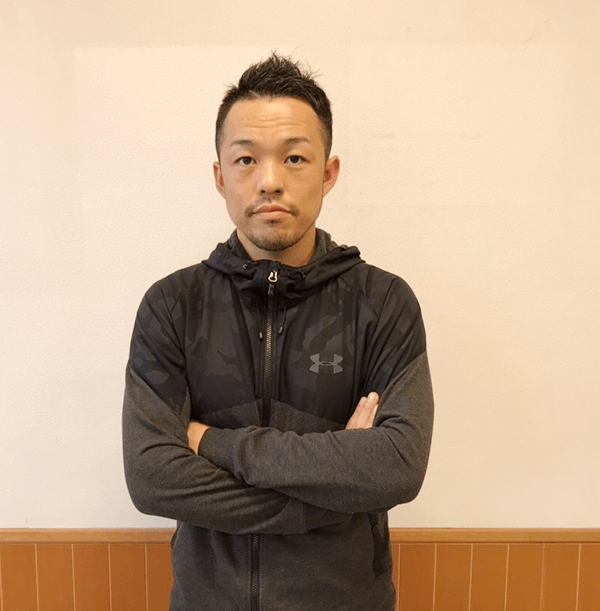
めぐり整体代表の菅井謙介です。いつまでも元気で、好きなことを続けてもらう身体づくりを提供することで、地元である下野市小金井への恩返しができたら幸せに思います。
詳しいプロフィールいつもブログをお読みいただきありがとうございます。栃木県下野市「めぐり整体」代表の菅井です。今回は、膝内側側副靭帯損傷について書いていきます。膝内側側副靭帯損傷は膝関節の靭帯損傷の中でも一番頻度が多いとされています。特にスポーツ動作での発生頻度が高いです。この記事では、膝内側側副靭帯の機能解剖と、靭帯損傷後のリハビリについて、どういうことに気を付けながら進めていくのかについて書いていきたいと思います。
膝内側側副靭帯の機能解剖
・膝内側側副靭帯は膝関節内側の安定を担う靭帯で浅層と深層に分けられる
・膝内側靭帯は筋肉、半月板、関節包にも付着して関節を安定させる役割
・伸ばしても曲げても膝関節全可動域で一定の張力を保っている
・膝が内側、足首が外側に向くような膝が捻じれた状態で損傷しやすい
膝内側側副靭帯損傷とは
膝内側側副靭帯損傷は、膝関節の靭帯損傷の中で一番発生頻度が多い靭帯損傷と言われています。受傷起点は、膝関節に過度の外反ストレス(膝が内側に捻じれる)が加わって発症します。損傷にも分類がされており、損傷しているが膝関節に不安定性を示さないものから(軽傷)、膝関節を伸ばした状態でも関節に不安定性を示すもの(重症)まであります。軽傷の場合、保存療法で十分な治療成績を残せますが、重症例である場合、他の靭帯損傷を合併していることが多く、手術適応となることが多いです。
膝内側側副靭帯損傷の分類と徒手検査
膝内側側副靭帯損傷の有無を確認する徒手検査には、外反ストレステストがあります。外反ストレステストとは、靭帯が緊張する方向に力を加えて、靭帯の制動が働くかを確認するものです。靭帯が緊張することで関節に制動がかかり関節が守られます。靭帯損傷により靭帯が緩んでいると、関節に制動がかからず、不安定に動いてしまいます。膝関節を軽く曲げた状態と、伸ばした状態で行います。伸ばした状態でも関節に不安定性が出る場合は、内側側副靭帯だけではなく、前十時靭帯損傷や後十字靭帯損傷の複合損傷が疑われます。
損傷後のリハビリについて
損傷程度により修復期間が変わります。修復期間は膝関節を固定し、靭帯の修復を待ちます。靭帯の修復をエコーで確認しながら、その状態にあったリハビリを進めていきます。固定後は関節の動きが悪くなり曲げ伸ばしが困難な状態ですので、可動域の改善を図りつつ筋力強化を進めていきます。可動域改善のポイントは、正確に制限因子を見つけ正常な関節運動を獲得すること、筋力強化のポイントは膝関節内側にある内側広筋の収縮を促すことが大切になります。
まとめ
・膝内側側副靭帯は膝関節内側の安定性を担う靭帯である
・膝が内側、足首が外側を向く膝が捻じれた状態で損傷することが多い
・内側不安定性が出ない軽傷の場合は保存療法、重症の複合損傷の場合は手術適応となることが多い
・損傷はストレステストで大まかに確認することができ、膝を伸ばした状態で不安定性が出る場合は複合損傷を疑う
・保存療法のリハビリは靭帯の修復期間と状態を確認しながら可動域と筋力の改善を図る
いかがでしたでしょうか?保存療法の場合は状態にもよりますが1~3ヵ月を目安に復帰を目指します。損傷後は関節不安定性により半月板や他の靭帯損傷にも繋がることが多いため、体幹や股関節を含めしっかりと筋力強化を図ることが望ましいです。膝だけのリハビリで終了してしまうと、その後、膝への負担になることが多いので注意してください。