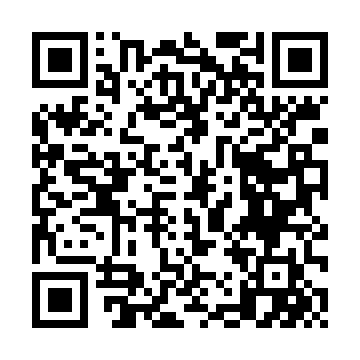対応症状
腰痛の方の多くが正しく〇〇をできていない?
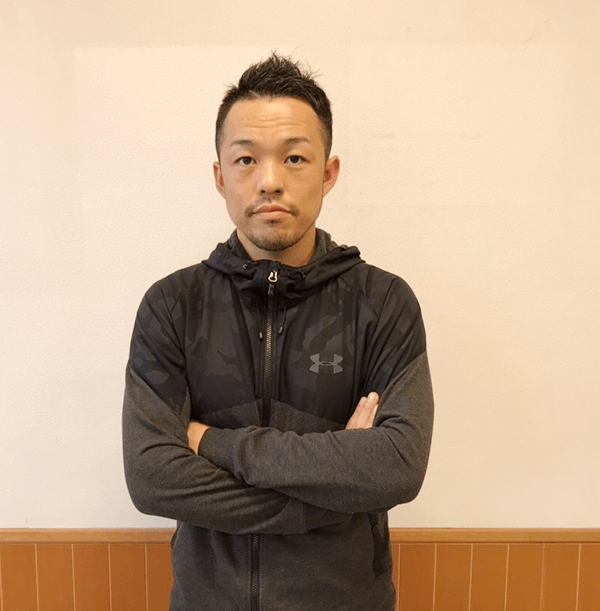
めぐり整体代表の菅井謙介です。いつまでも元気で、好きなことを続けてもらう身体づくりを提供することで、地元である下野市小金井への恩返しができたら幸せに思います。
詳しいプロフィールいつもブログをお読みいただきありがとうございます。
皆さまの中には、慢性的な腰痛でお悩みの方もいらっしゃると思います。私は普段から腰痛の方を多く施術させていただいていますが、腰痛の方にはある共通点があります。それは、正しく呼吸ができていないということです。正しい呼吸は横隔膜というインナーマッスルを使いますので、きちんとできるだけでも腰痛予防になると考えられます。この記事では、呼吸と腰痛の関係や、呼吸の仕組みについてお伝えしていきます。
呼吸は横隔膜をたくさん使う
1日で何回くらい呼吸をしているかご存知ですか?正解は、1日で約2万3千回といわれています。その呼吸にはインナーマッスルである横隔膜が関与しています。息を吸った時に横隔膜が下がり、吐いた時に横隔膜が上がります。正しく呼吸ができていると、たくさん横隔膜を使うので良いのですが、腰痛の方の多くは、ほとんど使えていないのが現状です。
横隔膜は腰痛と関係の深い腸腰筋と繋がっている
インナーマッスルである横隔膜は、腸腰筋という股関節と腰を繋ぐ筋肉と筋膜の連結があります。腸腰筋は、腰痛と関係が深く、固まった状態になると腰痛の原因にもなります。反り腰になっている人は、腸腰筋が固くなっている場合が多いです。その腸腰筋と横隔膜は筋膜で繋がっているので、呼吸により横隔膜を動かせていないと腸腰筋も固くなってしまいます。
横隔膜が動くことでお腹に圧(腹腔内圧)がかかる
横隔膜を使って呼吸ができることのメリットは、お腹に圧をかけられることです。息を吸った時に横隔膜が下にさがることで、横隔膜が内臓を下に押し下げ、お腹に圧がかかります。息を吸った時に、みぞおちの高さの肋骨が横に広がる、お腹が風船のように360°膨らんでいることがポイントです。
腹腔内圧が体幹を安定させる
横隔膜が使えるようになると、お腹に圧がかかるため、息を吸った時にお腹が360°膨らみ風船のようにパンと張った状態になります。この腹圧のかかった状態が体幹を安定させます。
体幹が安定しないと腰の筋肉が過剰に働き腰痛のきっかけになる
呼吸によって体幹を安定させられない場合、他のどこかで体幹を安定させなければなりません。その代わりに使われるのが背中や腰の筋肉です。背中や腰の筋肉を使って体を安定させようとします。その結果、背中や腰の筋肉には疲労がたまり固くなっていきます。それが腰痛の原因の1つにもなります。
あなたは大丈夫?正しい呼吸を確認する
それでは、意識してほしい呼吸の仕方を以下にまとめます。
1 鼻から吸って、鼻から吐く(運動している時は口から吐いてOKです)
2 吸った時はお腹と肋骨を膨らませる
*仰向けで行ってもOKです。お腹の中に風船をイメージして、吸った空気をお腹の風船に送り込むイメージを持ち、お腹を360°膨らませる意識(背中側も横側も膨らませる)を持ちます。この時、みぞおちの高さに位置する肋骨が横に広がると良いです。お腹が膨らまない、肋骨が広がらない人がほとんどです。
吸った時に腰が反ってしまう人や、膨らませる感覚がわからない人も多いです。
3 吐いた時は肋骨が下にさがって閉じる
*吸った時に肋骨は広がります。吐いた時はその逆で、下にさがりながら閉じていきます。この肋骨の動きが起こらない人がほとんどです。お腹に力が入り、みぞおちがグッと固まらないように注意しましょう。
まとめ
・呼吸は腰痛と関係する。
・呼吸はインナーマッスルである横隔膜を使う。
・息を吸った時に横隔膜は下がり、吐いた時に上がる。
・呼吸ができていないと、腰痛と関係の深い腸腰筋が固くなる。
・呼吸ができるとお腹に圧がかかり、体幹が安定する。
・お腹に圧がかからないと背中や腰の筋肉が変わりに働き固くなる。
・腰痛の原因の1つになる。
いかがでしたでしょうか?今回は、呼吸と腰痛についてお伝えしました。1日約2万回以上する呼吸ですので、できているか、できていないかは大きな差になってきそうですね。呼吸で普段から意識できることがありましたら、実践していきましょう。